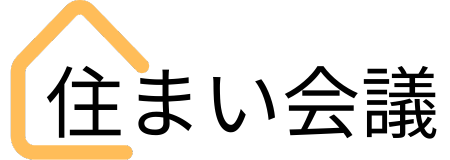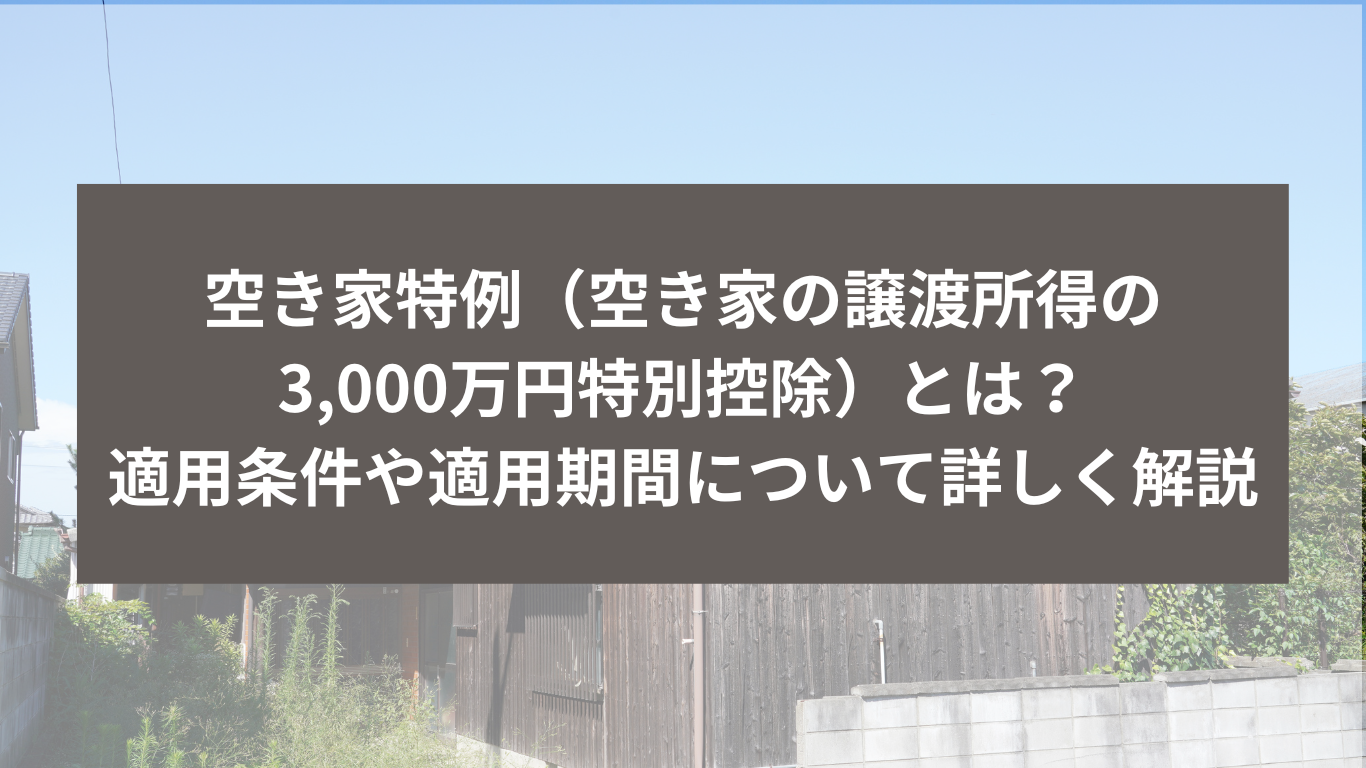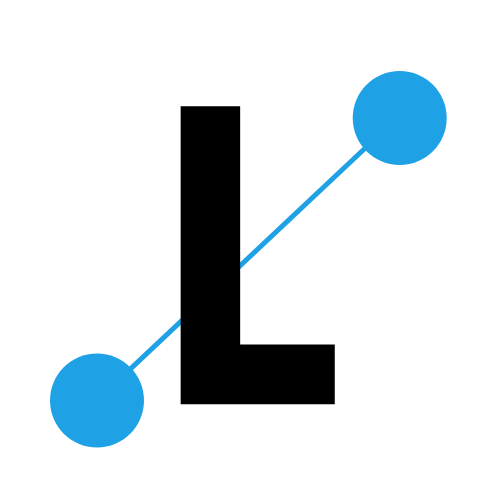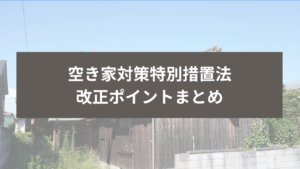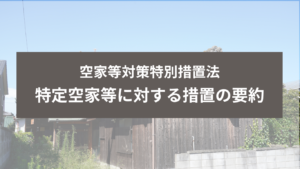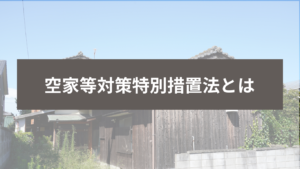「空き家の譲渡所得に対する3,000万円の特別控除」「空き家の3000万円控除」「空き家特例」についてお調べですか?
本記事では、空き家特例の特別控除について、条件や適用期間について解説していきます。
- 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)とは何か
- 控除を受けるための条件
- いつまで控除を受けられるか
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)とは
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、被相続人(亡くなって相続される方)が一人で住んでいた家を相続した相続人が、相続開始の日から3年以内(正確には相続を開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)に、売却などで譲渡した場合に、一定の条件を満たしていた場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する、という制度です。
ここで重要なポイントは、「譲渡所得とは何か」と「譲渡所得の計算」です。
ポイント①【所得税(譲渡所得)】
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は譲渡所得にはなりません。
ポイント②譲渡所得の計算
収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除楽=課税譲渡所得金額
ちなみに、通常の土地や建物の取引では、取得から経過した年数によって、「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かによって税率が異なり、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されています。
空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除の具体例、計算
【「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の適用時の計算式】
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
仮に譲渡収入6,000万円、取得費2,000万円(所有期間5年)、譲渡費用200万円であった場合は、
譲渡所得(800万円)=7,000万円 -(2,000万円+200万円)-3,000万円
という計算になり、税率は下表のとおり、その売却した不動産の所有期間に応じて2通りの税率が適用されます。下表の所有期間については、「譲渡日」ではなく「譲渡年の1月1日時点」で判定するためご注意ください。
| 区分 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
相続の場合は「被相続人がその資産を取得した日」にさかのぼって所有期間を判定
相続によって取得した資産については、「相続人が財産を承継した日」ではなく「被相続人がその資産を取得した日」にさかのぼって所有期間を判定できるため、5年超の所有期間を満たしやすくなるでしょう。
| 特例を適用する場合 | 譲渡所得:800万円、税額:162.52万円 |
| 特例適用しない場合 | 譲渡所得:3,800万円、税額:771.97万円 |
上記の場合は約600万円の税金が減額されることになります。
相続や贈与によって取得した資産の取得費について
相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、相続人が取得するための費用ではなく、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。
参照:国税庁HP(No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期)
※取得費が分からない場合などには、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
具体的な税金についてのご相談は税理士へご相談ください。税理士法上、税理士以外が具体的な税務に関する相談を受けることは、無料であっても違法となるため、当メディアではご相談を受けることができません。
相続空き家の3000万円特別控除はいつまでか
「空き家特例」は期限が延長され、適用期限が令和9年(2027年)12月31日までとなりました。
また、現行制度では、譲渡前に耐震改修工事や建物の取り壊しをする必要がありましたが、令和6年(2024年)1月以降に行う譲渡については、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震改修や取り壊しをすれば特例を適用することができるようになります。
一方で、相続人等が3人以上いる場合の特別控除額は、上限が3000万円から2000万円に減額されます。
相続空き家の3000万円特別控除の要件は?
まず対象となる「空き家」の要件は、以下の3つです。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において亡くなった人以外に居住をしていた人がいなかったこと
次に特例が適用される要件は以下のとおりです。
- 譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと
- 空き家を売るか、空き家とその敷地を売る場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
- 相続または遺贈により取得した空き家を取壊したあとに、その敷地を売る場合は、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと
- 相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること(相続人が複数の場合は1人につき1億円ではなく、合算した売却代金が1億円以下であること)
- 売った空き家等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと
- 同一の亡くなった人からの相続または遺贈により取得した空き家等について、空き家特例の適用を受けていないこと
- 空き家等の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと
まとめて以下に整理しながら詳細を解説します。
| 被相続人居住用家屋 | 相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと (老人ホーム等への入所で一定の場合は適用可) |
|---|---|
| 相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと | |
| 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く) | |
| 土地等 | 相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等 |
| 対象者 | 相続により「被相続人居住用家屋」及びその敷地の用に供された土地等を取得した個人 |
| 適用期間 | 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡 |
| 譲渡期限 | 相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡 |
| 譲渡対価限度額 | 譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く |
被相続人が一人で暮らしていた
この特例は空き家をなくすことを目的にしていますので、被相続人が亡くなられた時点で一人暮らしの場合に限られます。被相続人に同居者がいなかった場合に限り、亡くなられた方が住んでいた空き家とその敷地を相続された方が売却して利益を得た場合に、その利益から3,000万円の特別控除が認められます。
昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地に限定
旧耐震の建物を新耐震基準を満たす耐震リフォームをしてから譲渡する必要があります。
ただし、2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡から、売買契約等に基づいて、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となり要件が緩和されました。
売買契約後の耐震改修や除却工事を行なった場合も、適用対象となります。
相続から譲渡まで引き続き空き家であること
相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないことが必要となります。つまり、相続から譲渡までの期間継続して空き家であることが要件です。
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)の必要書類
空き家特例を適用するには、確定申告書に要件を満たすことを証明できる以下の書類を添付する必要があります。
- 譲渡所得の内訳書
- 売った空き家等の登記事項証明書で次の3つの事項が明らかになっているもの
- 売った人が亡くなった人の居住用家屋および居住用家屋の敷地等を亡くなった人から相続または遺贈により取得したこと
- 空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 空き家の所在地を管轄する市区町村長に申請することで交付される「被相続人居住用家屋等確認書」
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることがわかる書類
なお、相続または遺贈により取得した空き家を取り壊した後にその敷地等を売った場合は、④の添付は不要です。
また、②の登記事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産にかかる不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することで、添付を省略することができます。
国税庁のチェックシート
適用要件や添付書類については、国税庁が「空き家特例チェックシート」を公表しています。控除を受けられるかどうか、事前に確認しましょう。
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)の手続きの流れ
3,000万円の特別控除を受けるためには、以下の流れで手続きを行ないます。
- 管轄の市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請する
- 被相続人居住用家屋等確認書の交付を受ける
- 被相続人居住用家屋等確認書などの必要書類を添えて確定申告を行なう
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)の注意点
相続空き家は「区分所有建物」は対象外
相続空き家の3,000万円特別控除の特例は「区分所有建物」が対象外となっているため、マンションの空き部屋売却には適用できません。
区分登記された二世帯住宅にも適用できない
区分登記された二世帯住宅にも適用できないので、登記事項証明書または固定資産税の納税通知書(区分登記されていれば家屋番号が別々)を確認してください。
相続から売却までに自分が居住したり賃貸などに出していたら適用されない
相続した空き家に自分が住む、あるいは第三者などに賃貸するなどすると、譲渡所得の3,000万円控除は受けられなくなるのでご注意ください。相続から売却まで継続して空き家であることが要件となっています。
譲渡価格が1億円以下でなければ3,000万円の特別控除は使えない
相続空き家(土地・建物)の譲渡価格は、固定資産税の清算額も合わせて1億円以下が要件となっています。共有名義で相続した空き家の場合も合算した金額が1億円以下になっている必要があります。
親族や同族会社への売却ではないこと
空き家の売却先は原則として第三者になるため、同一生計の親族や同族会社に売却すると、3,000万円の特別控除は適用できません。
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)と併用できる制度
空き家特例の適用と併用でき、減税につながる制度があります。適用可能かどうかの個別具体的な相談は税理士に相談してみてください。
- 小規模宅地等の特例(相続税の申告時)
- 居住用財産の3000万円控除
一方で、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる「取得費加算の特例」は併用できません。
空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)のよくある質問
- 共有で相続し売却した場合、控除額はどうなるか
-
共有で相続した場合なども控除額は変わりません。一人当たりの控除の上限は3,000万円です。
- 被相続人が老人ホームに入所していた場合はどうなるか
-
空き家の所有者だった被相続人が亡くなる直前まで老人ホームに入居していた場合も、一定の要件を満たすと3,000万円の控除の対象となります。
※この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。(国土交通省HPより)
この場合、被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な要件と証明書類は以下のとおりです。
要件 証明書類 被相続人が要介護または要支援認定を受けていたこと 被相続人の介護保険被保険者証等 相続直前まで老人ホームにおり入所直前まで対象の家屋に住んでいたこ 被相続人の除票住民票の写し老人ホームの名称や所在地などが確認できる書類(入所時の契約書等) 老人ホームの入所直前に被相続人の他に居住者がいなかったこと 相続人の住民票の写し(老人ホームの入所直前から譲渡時までの住所がわかる書類) 老人ホームの入所後に他者の居住や事業に使用されていないこと 相続人の住民票の写し電気ガスなどの中止日および契約者がわかる書類等 - 譲渡後に耐震改修工事または取り壊しを行なった場合は対象になるか
-
一定の条件で対象となります。譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合は、控除の適用対象に加わることとなりました。なお、この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
まとめ
これから、空き家の相続が増加していく中で、空き家特例(空き家の譲渡所得の3 000万円特別控除)は非常にメリットが大きく、条件に合致するのであれば積極的に利用した方が良い制度です。
相続した家を空き家のまま放置しておく方は少なくありません。しかし、上記の制度には「3年以内」という適用条件がありますので、相続した空き家を売却することで多額の税金が発生してしまう場合は、3,000万円控除を受けるために、改修や取り壊しを前提に売却をしていくのも選択肢の一つです。
空き家を相続したタイミングで、そのまま放置せず、3000万円控除の制度を利用して3年以内に処分を検討することがまずは重要です。そのためには、ご自身が相続したお家の売却価格や耐震工事の費用、解体費用を調べておくことが重要になります。
物件の売却査定のご相談
弊社では、岐阜県・愛知県を中心とした東海エリアや首都圏エリアでの売却のご相談を無料で承っています。
| 会社名 | 合同会社LEOSENSE |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県安八郡輪之内町大藪1203番地6 |
| 免許番号 | 岐阜県知事(1)第5251号 |
| 所属団体 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 |
| 公式サイト | https://leosense.co.jp/ |
- 査定は完全に無料ですか?
-
弊社が行う査定は無料のサービスです。
査定後、弊社との間で媒介契約を締結し、無事売買が成立した際にはじめて仲介手数料が発生します。 - 媒介契約は必須ですか?
-
媒介契約は必須ではありません。査定額を確認のうえ、そのまま所有し続けるご判断いただくことは可能です。
- 査定の方法を教えてください
-
対象物件の基本情報に基づいて、類似物件の取引価格のほか公示地価、路線価なども加味して査定価格を算出します。
- 訪問査定は可能ですか?
-
物件のエリアによって訪問査定も可能です。別途問い合わせにてご相談ください。
以下のフォームからお問い合わせください。
所有物件の管理(空き家管理)のご相談
弊社では、現在居住していないお家(空き家、空きマンション)の管理代行サービスを行なっています。
相続やお引っ越しなどで所有している空き家の管理に以下のお悩みをお持ちでないですか?
- メンテナンス不足で設備が劣化している
- 近隣住民からクレームが入った
- 地域で空き巣被害が増えている
- 維持管理に交通費や時間がかかる
- ゴミの不法投棄で異臭が発生している
- 本来の所有者が病気や怪我で一時的に管理できない
- 郵便物に重要な書類が届いている
2023年空き家法が改正され、所有者の責任が強化されました。管理不全のまま放置することで、行政から勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が増えてしまうだけではなく、行政代執行による費用請求などを受けてしまう可能性があります。
相続や引っ越しなどで空き家となってしまった大事なお家の資産を守るため適切に管理することが重要です。