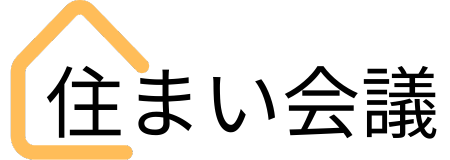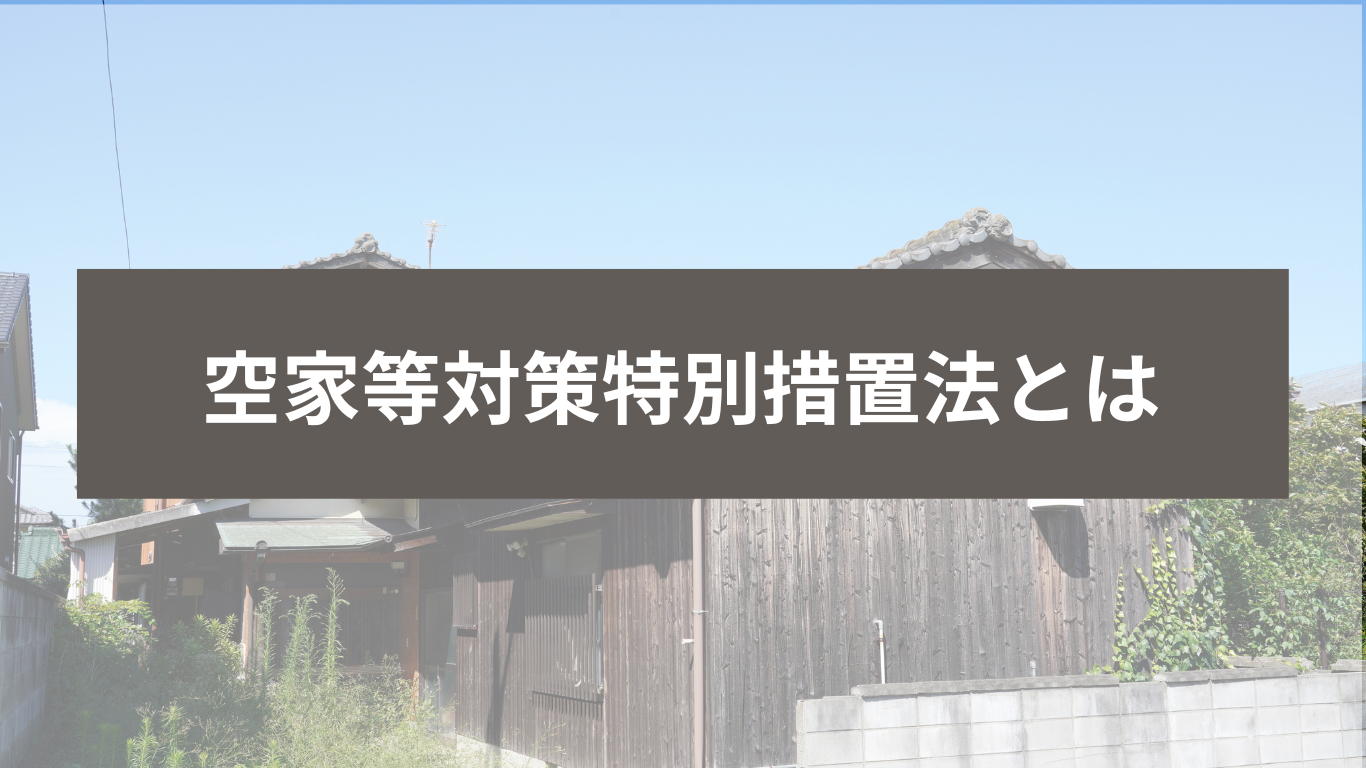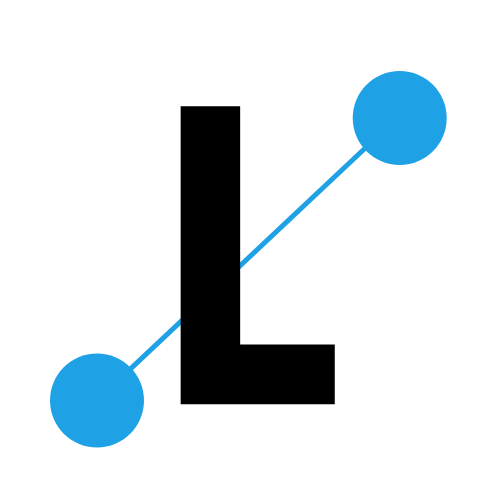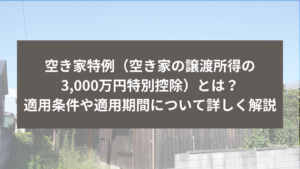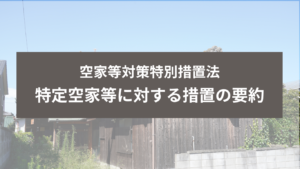最近「空家法」「空家対策特措法」という言葉を耳にする方も増えてきたのではないでしょうか。
日本では放置された空き家が社会問題となっています。この問題に対応するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(クリックすると展開します。)
平成二十六年法律第百二十七号
空家等対策の推進に関する特別措置法
(目的)
第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(空家等の所有者等の責務)
第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市町村の責務)
第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(基本指針)
第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
3 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(空家等対策計画)
第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
二 計画期間
三 空家等の調査に関する事項
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
六 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
(協議会)
第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(都道府県による援助)
第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
(立入調査等)
第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第十一条 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(空家等及び空家等の跡地の活用等)
第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(特定空家等に対する措置)
第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
7 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
13 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。
(財政上の措置及び税制上の措置等)
第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(過料)
第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
2 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和五年六月一四日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、空き家の問題を緩和するために以下の重要な規定を設けています。
- 空き家の実態調査と管理
- 空き家の跡地活用と特定空家指定
- 罰則と行政代執行
本記事では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に関して、空き家を所有している、もしくは空き家を所有するかもしれない方に向けて分かりやすく説明したいと思います。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2023年12月に改正が予定されており、新たに「管理不全空き家」という概念が追加されました。本記事と併せて、改正ポイントをまとめた記事についてもご参考いただけると幸いです。
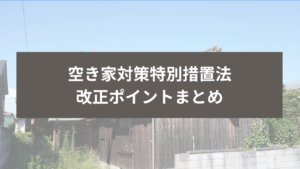
空き家問題とその社会的影響
前提として、空き家が問題視される背景について解説します。
空き家がもたらす影響
まず、空き家は単なる「使われていない建物」ではありません。それぞれの空き家が持つ問題点を考えてみましょう。
- 治安への影響: 放置された空き家はしばしば犯罪の温床になります。不法侵入や器物損壊、場合によっては火災の原因ともなり得ます。地域の安全を守るためにも、これらのリスクをどう低減するかが重要です。
- 環境への影響: 荒れ果てた空き家は地域の景観を損なうだけでなく、害虫や野生動物が繁殖する原因ともなります。また、老朽化した空き家は災害時の危険性を増大させることがあります。
- 経済への影響: 空き家が集中する地域では、地価の下落や地域経済の衰退を招くこともあります。活気のあるコミュニティを維持するためにも、これは大きな問題です。
対策の必要性
こうした問題を解決するために、国や自治体が行うべき対策は何でしょうか?この問題に対処するため、政府は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定しました。この法律は、空き家の適切な管理と活用を促進し、上記の問題を緩和することを目的としています。
私たち専門家として、空き家の所有者や地域住民の皆さんが、この法律の重要性を理解し、適切な対応をとれるよう支援しています。
次章では、この法律の概要と目的について、もっと詳しく解説します。
空家等対策特別措置法の概要
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家等対策特別措置法)は、日本国内の増加する空き家問題に対応するために制定された法律です。この法律は、空き家の所有者や自治体に対し、空き家の適切な管理と活用を促進するための枠組みを提供しています。
法律が成立した背景
この法律の成立背景には、複数の要因が絡み合っています。
日本では、新築至上主義」のもと、住宅業界は新築住宅を大量供給することで成長してきました。そして、高齢化の進展や人口減少、都市部への人口集中などにより、特に地方で空き家が増加しています。
これらの空き家は、治安の悪化、景観の低下、防災上のリスク増大など、さまざまな社会的問題を引き起こしています。
法律の目的
この法律の主な目的は、空き家による社会的な問題を緩和し、安全かつ魅力的な地域コミュニティを維持することです。具体的には、以下のような点に焦点を当てています。
- 空き家の適切な管理の促進: 空き家の所有者に対し、その財産を適切に管理する責任を課し、必要に応じて自治体が助言や指導を行います。
- 特定空家の指定と管理強化: 適切に管理されていない空き家については「特定空家」として指定し、より強力な管理措置を講じることができます。
- 自治体の権限強化: 空き家の所有者が不明または管理を怠っている場合、自治体が積極的に介入し、必要な措置を取ることができます。
- 空き家の有効活用促進: 空き家の再利用やリノベーションに関する支援策を通じて、空き家の効果的な活用を推進します。
この法律によって、空き家の所有者はより大きな責任を負うことになりますが、これは地域社会全体の安全と発展のために不可欠なステップです。次章では、空き家の定義と所有者に求められる具体的な義務について詳しく説明します。
空き家の定義と所有者の責任
「空家等対策特別措置法」において、空き家の定義と所有者の責任は非常に重要なポイントです。
空き家の定義
(定義)
空家等対策の推進に関する特別措置法
第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
空き家とは「居住その他の使用がなされていない建築物又はこれに附属する工作物」を指します。ガイドラインによる具体的には、以下のような基準が設けられています。空き家の判断は、総合的な状況から判断されます。
- 居住の不在: 1年以上継続して、誰も居住していない状態
- 使用の不在: 建物が事務所や店舗などとして使用されていない状態
- 総合的な判断基準: 人の出入りの有無や水道・電気・ガスなどのインフラの使用状況
所有者の責任
(空家等の所有者等の責務)
空家等対策の推進に関する特別措置法
第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
空き家の所有者は、その不動産を適切に管理する責任があります。これには以下のような義務が含まれます。
- 建物の維持管理: 建物の老朽化防止、安全確保のための定期的なメンテナンスと修理
- 敷地の清掃と整備: 敷地内の清掃や草木の手入れを行い、見た目の良好な状態を維持する
- 防災対策: 倒壊や火災の危険性を低減するための適切な対策を講じる
- 自治体の指導・勧告に対する対応: 市町村からの助言や指導に対し、適切に対応する
法的措置
適切な管理が行われていない場合、市町村は所有者に対して助言、指導、勧告、最終的には命令を出すことができます。これらの指示に従わない場合、所有者は罰則の対象となる可能性があります。
また、税制的にも不利益を被る可能性があります。空き家の所有者としては、そのような不利益を避けることが重要となってきます。
次章では、空き家の管理に関する具体的な対策と、所有者の方が気を付けるポイントについて書いていきます。
空き家管理のポイント
1. 定期的な点検とメンテナンス
- 建物の点検: 定期的に建物をチェックし、必要な場合は修理や補強を行いましょう。特に屋根や外壁に問題があると劣化が激しくなるので特に確認してください。
- 設備の維持管理: 設備は使わないと劣化してしまいます。水道の通水、電気、ガスなどの設備の定期点検を忘れずに行うことで建物の寿命を延ばすことができます。
2. 敷地の清掃と整備
- 草木の手入れ: 敷地内の草木を定期的に剪定し、きれいに保ちましょう。手入れがされていないことで、空き家だと認識されると空き巣や犯罪の温床となってしまいます。また、近隣住民からのクレームにつながるケースもあります。
- ゴミや不要物の撤去: 敷地内の清潔を保つため、定期的にゴミや不要物を撤去してください。長期間空き家として放置されると、不法投棄やゴミのポイ捨ての対象となってしまう恐れもあります。
3. 近隣とのコミュニケーション
- 近隣住民との良好な関係: 定期的に近隣住民とコミュニケーションを取り、地域の一員として協力し合いましょう。
4. 法律と自治体の指導への対応
- 法律の遵守: 「空家等対策特別措置法」をはじめ、「建築基準法」や「消防法」など、関連する法律がありますので、法令に違反している状況にないかは最低限確認をしておきましょう。
- 自治体の指導: 市町村からの助言や指導が入れば、迅速に対応しましょう。放置した場合に、最悪の場合罰則が適用されます。
次章では、特定空家の指定とその意味について、さらに詳しく説明します。
特定空家の指定とその意味
「空家等対策特別措置法」に基づき、特定の条件を満たす空き家は「特定空家」として指定されることがあります。特定空家の指定は、空き家が周囲の環境や地域社会に与える影響を考慮した上で行われます。ここでは、特定空家に指定される基準と、その意味について解説します。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
空家等対策の推進に関する特別措(第二条2項)
特定空家に指定される基準
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家に指定された場合の影響
特定空家に指定されると、以下のような影響が生じる可能性があります。
- 強化された管理義務: 特定空家の所有者には、通常の空き家以上に厳しい管理義務が課されます。
- 行政の介入: 市町村は特定空家に対し、改善命令を出したり、最終的には行政代執行によって強制的に問題を解決することができます。
- 罰則の適用: 改善命令に従わない場合、罰金が科されることがあります。
特定空家等に認定されるまでのプロセスと認定された後のプロセスについて解説します。
特定空家等の指定プロセスについて
- 空き家の特定: まず、市町村は地域内の空き家を特定します。これは、地域内の空き家の実態調査によって行われ、空き家の状態、利用状況、保安上のリスクなどが評価されます。
- 問題の特定: 特定された空き家の中で、倒壊の危険がある、衛生上の問題を引き起こしている、または景観を著しく損なっているなどの問題がある空き家を特定します。
- 特定空家等の指定: 上記の基準に該当する空き家について、市町村長は「特定空家等」として正式に指定します。この指定は、空き家が地域社会に及ぼす潜在的なリスクや問題に基づいて行われます。
- 所有者への通知: 特定空家等として指定された場合、市町村はその空き家の所有者に通知します。この通知には、指定の理由と所有者が講じるべき措置が記載されます。
- 助言と指導: 市町村は、特定空家等の所有者に対し、必要な措置を講じるよう助言や指導を行います。これには、修繕、除却、立木の伐採など、周辺の生活環境を保全するための措置が含まれることがあります。
- 勧告と命令: 助言や指導にもかかわらず改善が見られない場合、市町村長は相当の猶予期限を設けて、必要な措置をとるよう勧告し、さらに改善がない場合は命令を出すことができます。
- 行政代執行: 最終的に命令に従わない場合、市町村は行政代執行法に基づき、必要な措置を自ら行うか、第三者に行わせることができます。
- 追加の措置と公示:標識の設置: 命令に関する情報は公示され、必要に応じて特定空家等に標識を設置します。
- 意見の聴取: また、所有者は意見書の提出や公開意見の聴取を請求することができます。
空き家を適切に管理することで、特定空家等に指定されないように管理をしていくことが重要となります。仮に特定空家等に指定されてしまった場合は、できるだけ迅速に行政指導に対処する必要があります。
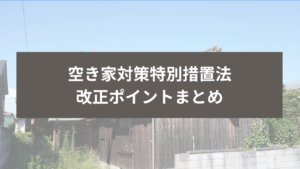
空き家の有効活用と支援策
特定空家と指定された空き家や、それ以外の空き家も含めて、これらの不動産を有効に活用する方法はいくつかあります。また、政府や地方自治体からは、空き家の所有者に対して様々な支援策が提供されています。
空き家の有効活用方法
- 賃貸物件としての活用: 空き家を改修し、賃貸物件として提供することで収入を得ることができます。
- リノベーションと再販売: 空き家をリノベーションし、住宅市場で再販売することも一つの方法です。
- コミュニティスペースとしての活用: 地域のコミュニティスペースやイベント会場として活用することで、地域社会に貢献できます。
- 農業や商業施設への転用: 農業用地や商業施設として利用することで、地域経済の活性化に繋がることがあります。
政府と自治体の支援策
- 改修費用の補助: 政府や自治体から、空き家の改修に関する補助金や助成金が提供されることがあります。
- 税制面での優遇措置: 改修や再販売に関連する税制面での優遇措置を受けることが可能です。
- アドバイザリーサービスの提供: 空き家の有効活用に関する相談やアドバイスを行政から受けることができます。
- 空き家バンク制度: 空き家を登録し、賃貸や販売のマッチングを行政がサポートする制度です。
所有者にとってのメリット
空き家を有効に活用することは、その物件の価値を維持または向上させることに繋がります。また、地域社会における空き家の問題を解決するための重要な一歩となり、地域コミュニティの活性化に貢献する可能性があります。
次章では、空き家を所有している、もしくは今後所有することになる方向けに、チェックリストを公開します。ぜひ、管理の際にご参考ください。
空き家所有者のためのチェックリスト
空き家の所有者として、適切な管理と有効活用を実現するためには、以下のポイントを定期的にチェックし、必要に応じて行動することが重要です。このチェックリストは、空き家を維持し、可能な限りその価値を高めるために役立ちます。
基本的なメンテナンスと管理
- 建物の定期的な点検: 屋根、外壁、基礎などの構造的な部分の点検を定期的に行います。
- 設備のチェック: 水道、電気、ガスなどの設備が安全であることを確認します。
- 草木の管理: 敷地内の草木の手入れを定期的に行い、整備された状態を維持します。
- 清掃とゴミの撤去: 定期的に清掃を行い、ゴミや不要物を撤去します。
法的義務と規制の遵守
- 法律の遵守: 「空家等対策特別措置法」、「建築基準法」、「消防法」などの関連法律を遵守しているか確認します。
- 行政の指導への対応: 市町村からの指導や勧告に対して、適切に対応しているか確認します。
防災対策
- 倒壊や火災の防止: 建物の安全性を確保し、火災報知器の設置など、防災対策を実施します。
近隣との関係
- 近隣とのコミュニケーション: 定期的に近隣住民との良好な関係を維持し、空き家の状態について情報共有します。
空き家の活用
- 活用の検討: 賃貸、リノベーション、コミュニティスペースへの転用など、空き家の有効活用について検討します。
- 支援制度の活用: 改修費用の補助や税制面の優遇措置など、利用可能な支援制度を確認します。
特に重要なのは、基本的なメンテナンスと管理、行政指導への対応となります。
遠方で管理自体が物理的に難しい場合は、NPOや空き家管理サービスを提供している事業者に委託することも一つの解決策です。また、最近では、空き家を活用したビジネスやリノベーションして再販する不動産事業者も増えてきました。家の状態を把握した上で、複数の選択肢から最適なものを選んでいくことが重要です。